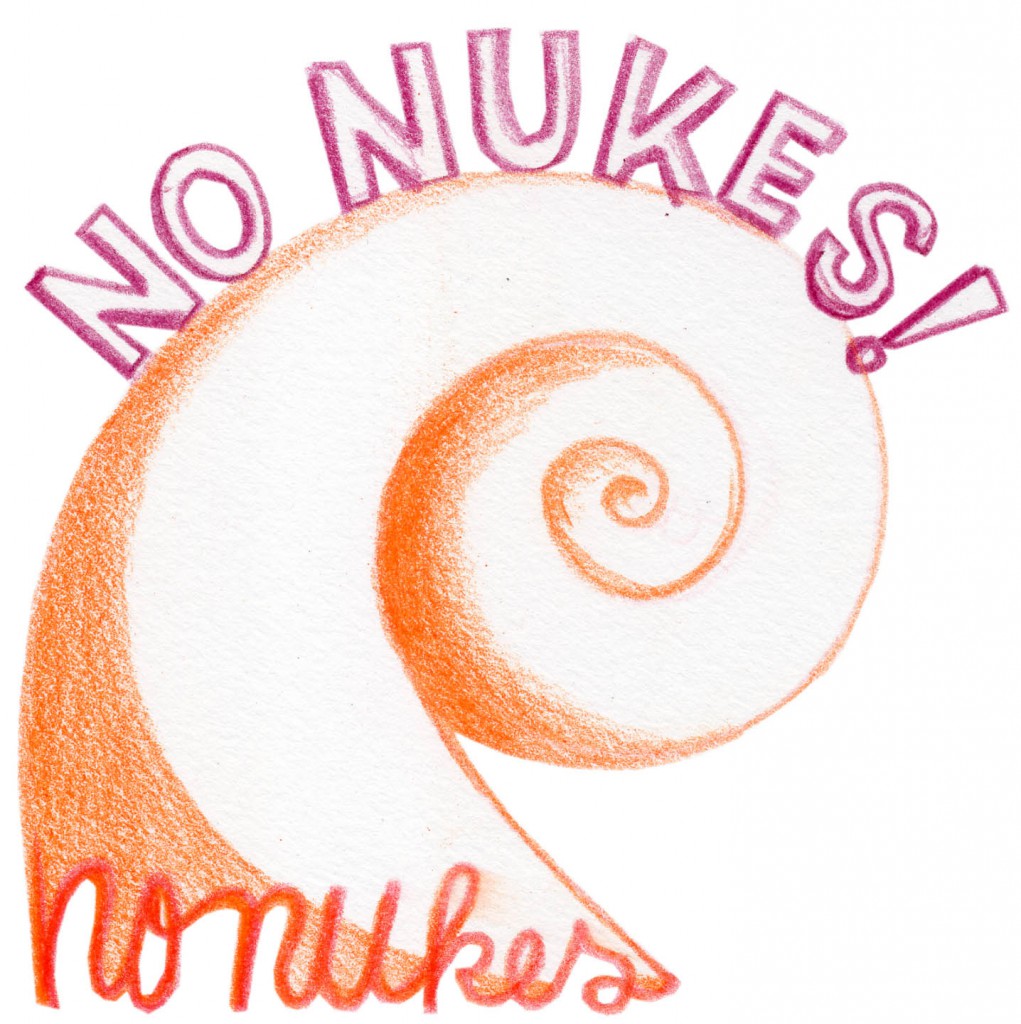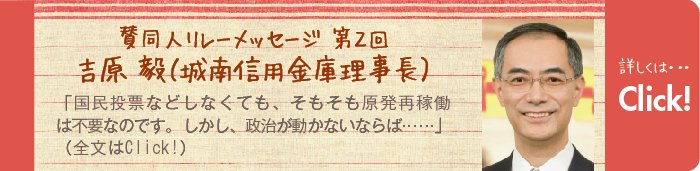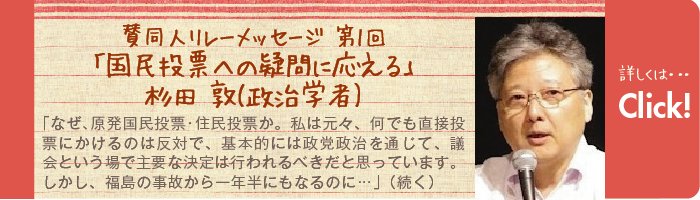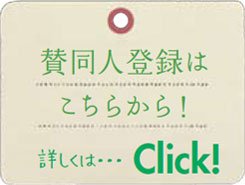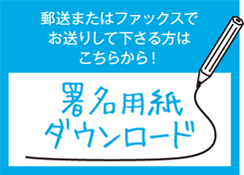リレーメッセージ「第3回 こぐれひでこ(イラストレーター)」

こぐれひでこ
1947年生まれ。パリで服飾デザインを学び、帰国後デザイナーとして活動後、イラストレーターに。人気ブログ「こぐれひでこのごはん日記」や多数の著書で、食や暮らし全般へのこだわりを発信中。
ふんわりとやわらかなタッチが見る人の気持ちを和ませる、こぐれひでこさんのイラスト。ブログや著作からは食に対する並々ならぬ好奇心と情熱が伝わってきます。
日常生活を大切にするこぐれさんは、原発「反対」の立場から賛同人になられ、メッセージとともに素敵なイラストを寄せてくださいました。
|
|
バックナンバー
2012年9月5日 | コメント/トラックバック(0) |
リレーメッセージ「第2回 吉原 毅(城南信用金庫 理事長)」

吉原 毅(よしわら つよし)
1955年生まれ。城南信用金庫理事長。1977年慶應義塾大学経済学部卒、同年城南信用金庫入職。1996年常務理事・市場本部長、その後、事務本部長、業務本部長を歴任し、2006年副理事長、2010年理事長
当会の著名賛同人からのメッセージをリレー形式で紹介する当コーナー。第2回目となる今回は、城南信用金庫の吉原毅理事長のメッセージを紹介します。
城南信用金庫は、福島第一原発の事故の直後に「脱原発宣言」を行っています。
城南信用金庫の脱原発に関する活動については、同信用金庫HPの「原発に頼らない安心できる社会をめざして」をご覧ください。
また、通販生活のホームページに「読み物:落合恵子の深呼吸対談:吉原毅さんの巻」が掲載されています。城南信用金庫が脱原発宣言をした理由や、脱原発に向けた具体的な活動について、吉原氏が語っています。
|
|
バックナンバー
2012年8月25日 | コメント/トラックバック(3) |
リレーメッセージ「第1回 杉田 敦(政治学者)」
「賛同人リレーメッセージ」では、本会に賛同する著名人の小論やインタビューを、週に一度のペースで掲載していきます。第1回目となる今回は、当会の活動を政治学の視点から支えてくださっている、杉田 敦・法政大学教授(政治学者)の最新の見解をご紹介します。
国民投票への疑問に応える
杉田 敦(政治学者)

杉田 敦(すぎた あつし)
1959年生まれ。法政大学教授。政治学者。『デモクラシーの論じ方―論争の政治』(ちくま新書)、『境界線の政治学』『政治への想像力』(以上、岩波書店)ほか。
議会政治・政党政治の長い伝統と実績をもつヨーロッパでさえ、原発問題がEU加盟の是非などと同様、国民投票にかけられている理由も、考えてみる必要があります。遠い将来まで人びとの生活を大きく左右する、きわめて重大な問題については、主権者の明確な判断に委ねる以外にないという考え方が根底にあると思います。
原発の是非を単一争点とする選挙に期待する方々もいるようですが、思い出していただきたいのは「小泉郵政選挙」の帰結です。単一争点を装い、自民党への批判票を吸収して成立した自民党政権は、郵政民営化だけを行ったわけではありません。原発政策では一致できても、他の政策には全く賛成できないような政党を、私たちは支援すべきでしょうか。
国民投票・住民投票をやっても、脱原発派が勝てそうにないので躊躇する、という意見も一部にあるようです。日本の有権者はまだ十分に政治的に成熟しておらず、経済界やその意を受けたメディアによってコントロールされているため、推進派に引きずられてしまう、というのです。これに対しては、きわめて重大な問題については主権者の判断を求めるしかないという原則論を、まず改めて確認したいと思います。
たしかに、過去に直接投票をした小規模の自治体の場合と異なり、たとえば国民という単位で、当事者としての責任ある議論を行うにはどうするか、という難しい問題はあります(それは、私もかねてから指摘してきたことです)。しかし、福島の事故以来、一般の人びとの意識は大きく変わっており、原発の是非については、他の問題と比べてきわめて高い関心が継続的に寄せられています。このことを過小評価し、有権者の意識の低さだけを強調して行くと、つきつめれば選挙を含めて、民主政治自体を否定することにもなりかねません。
国民投票よりも、選挙や街頭の運動に力を注ぐべきだという意見もあります。しかし、私たちは、そういったさまざまなやり方のうちのどれかを選ばなければならないのでしょうか。むしろ、いろいろな形で原発問題への関心が高まれば、それは他の運動にも波及効果をもたらすのではないでしょうか。想い起こすべきは、日本の戦後の社会運動の分裂の歴史です。運動のあり方をめぐって四分五裂し、結果的に現状維持派を利するということの繰り返しでした。原子力発電を今後も維持し、増やして行くのか、それとも停止し、減らして行くのか。この大きな対立軸を見失うことなく、運動を進めて行きたいと思います。
2012年8月13日 | コメント/トラックバック(12) |